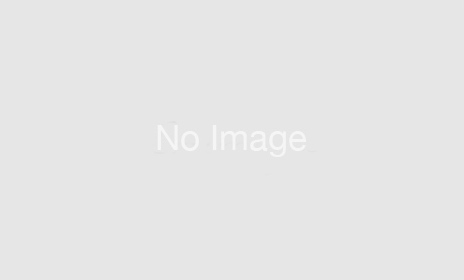幸市民館・図書館の改修について
◆野田雅之 おはようございます。私は、通告に従いまして一問一答で3問質問いたします。
初めに、妊産婦、乳幼児に対する防災の取組について伺います。本年元日に発生した能登半島地震から間もなく1年がたとうとしております。大きな被害が出た能登半島での教訓は、我々川崎市にとっても生かしていかなければならず、備えを進めなければなりません。3月の予算審査特別委員会では、災害時における妊産婦、乳幼児やその家族に対する避難所の取組について伺いました。そこでは、妊産婦の心身の健康管理や生活環境などの配慮が必要な部分があり、専門的な判断や経験が求められ、災害の状況に応じて避難所補完施設を利用するなど、被災された妊産婦等が安心して安全に避難生活を送るための課題整理から始めるとのことであり、加えて、その上で、妊産婦等に特化した避難所の検討や関係団体との意見交換など、関係局区と連携して取り組むとのことでありました。6月の一般質問では、その後の進捗を問い、今後、関係局区と連携して関係団体と意見交換を進め、妊産婦が安心して避難生活が行えるよう、対応方法について検討を進めるとの答弁でした。あれから半年が経過し、進展があるのが当然と考えますが、その後の進捗状況を危機管理監に伺います。
◎危機管理監(柴田一雄) 妊産婦等の避難所についての御質問でございますが、災害発生時の避難所生活において、要配慮者に区分される妊産婦や乳幼児等に対しましては、健康管理や生活環境などの配慮が必要な部分があると認識しておりまして、本年11月に川崎市助産師会と関係局とで意見交換を行い、発災時における妊産婦等への支援方法についての課題や今後の連携に当たっての要望等について意見を伺い、共通認識を図ったところでございます。今後につきましても、引き続き関係局区と連携して、関係団体と意見交換を進め、妊産婦等が安心して避難生活を行えるよう、対応方法について検討を進めてまいります。以上でございます。
◆野田雅之 3月、そして6月にも取上げさせていただきました。先月には川崎市助産師会と関係局で意見交換を行い、支援方法についての課題や連携についての要望を伺って、共通認識を図ったとのことであります。引き続き関係局区が連携し、実のある制度の構築をお願いいたします。3月の質問では、最終的には妊産婦及び乳幼児、また、その家族に特化した専用避難所の指定を強く要望し、検討にも触れていただきました。ぜひともその有効性を理解し、前進していただくようお願いいたします。また改めて進捗の確認、今後の方向性などは取り上げてまいります。
次に、扇島地区における水素供給拠点の保安に関する取組について伺います。本市では、JFEスチール株式会社東日本製鉄所京浜地区の高炉等休止に伴う土地利用方針において、扇島地区と先導エリアの一部をカーボンニュートラルエネルギーゾーンと位置づけ、水素の供給拠点を設置、日本初の大規模水素サプライチェーンの構築に向けた国のグリーンイノベーション基金事業、液化水素サプライチェーンの商用化実証の水素受入れ地として選定されているところであります。現在、4年後の2028年度から商用化実証、一部供用開始を目指し、関係企業により水素受入れ拠点の整備に向けた検討が進められていると認識をしておりますが、整備される施設の概要や現在の進捗状況について、臨海部国際戦略本部長に伺います。
◎臨海部国際戦略本部長(玉井一彦) 液化水素サプライチェーンの商用化実証についての御質問でございますが、まず、実証事業の概要につきましては、日本水素エネルギー株式会社が中心となり、扇島地区に液化水素の受入れ・出荷設備や貯蔵タンク等から構成される液化水素基地を整備するとともに、液化水素運搬船を建造し、2030年度までを目途に、商用規模での機器の性能確認や基地の全体運用、液化水素運搬船による外洋航行時の運用等の技術実証を行うものでございます。実証事業の終了後は、整備した設備を活用し、商用開始を目指しているところでございます。次に、進捗状況につきましては、令和7年度の液化水素基地の工事着手に向け、環境影響評価の手続、許認可の取得、各種設計・検討等を進めているところと伺っております。以上でございます。
◆野田雅之 現在、令和7年度の液化水素基地の着手に向け許認可の取得や各種設計・検討等を行っているとのことであります。商用規模での水素の貯蔵タンクなどが整備されているとのことですが、どのぐらいの量の水素を貯蔵し、また、どのぐらいの圧力の水素ガスを取り扱う計画なのか伺います。また、現在国内の他都市においても、同様の水素貯蔵タンクが整備されている事例があり、これらの施設の規模についても伺います。
◎臨海部国際戦略本部長(玉井一彦) 液化水素基地についての御質問でございますが、基地の規模につきましては、技術実証から商用の初期段階においては、5万立方メートルの液化水素を貯蔵可能なタンクを1基整備する計画でございまして、貯蔵タンクの内圧は、おおよそ大気圧程度になると伺っております。この規模は、2015年度から神戸空港島で実施されております液化水素サプライチェーンのパイロット実証事業の貯蔵タンク約2,500立方メートルの20倍の容量となり、世界的にも最大級となる見込みでございます。また、水素ガスとしてパイプライン等に供給する圧力につきましては、詳細は検討中とのことでございますが、社会実装・商用時には、従来のガス火力発電所に用いられる圧力と同程度として供給可能なよう、関連設備を計画していると伺っております。以上でございます。
◆野田雅之 2015年度から実施されている神戸によるパイロット実証事業の貯蔵タンクの20倍の容量で、世界最大級になるとのことでありました。その規模の大きさが比較でよく分かりました。それにはしっかりとした準備が必要となるはずであります。川崎の臨海部においては、これまでも水素を扱っていますが、新たに大規模なタンクで水素を貯蔵することになります。安全対策は極めて重要になるはずであります。保安対策に関する考え方、国の動向や本市の検討状況を伺います。
◎臨海部国際戦略本部長(玉井一彦) 液化水素基地における保安についての御質問でございますが、川崎臨海部においては、立地企業が、これまでも石油精製や化学産業における生産活動において、水素を利用しており、高圧ガス保安法や消防法などの関係法令に基づき、消防局等の指導の下、設備の整備や維持管理、保安対策等が講じられるとともに、事故等の発生時に迅速に対応できるよう取り組んでいるところでございます。一方、国においては、令和5年度に世界最先端の日本の水素技術で水素社会を実現し、安全・安心な利用環境を社会に提供することを目的とする水素保安戦略の中間取りまとめを公表しております。その中で、まず、既存法令により迅速に対応することとしており、その後、技術実証により得られた安全確保を裏づける科学的データ等を踏まえて、社会実装・商用段階においては、新たな技術基準を設定することとしております。こうしたことを踏まえ、扇島地区に整備する液化水素基地の保安対策につきましては、高圧ガス保安法等の関連法令に適合する施設として整備する計画となっておりまして、実証段階では、これまで液化水素や高圧ガスを取り扱ってきました関係事業者の知見を活用するとともに、関係機関に保安上の基準への適合性を確認することなどにより、迅速な対応を図ることとしております。また、社会実装・商用段階では、新たに策定される技術基準など、国の検討状況を踏まえながら、保安対策につきましても、段階に応じて具体的な検討を行うと伺っております。本市といたしましても、安全かつ効率的、効果的な事業実施が重要であると考えておりますことから、国や関係事業者、庁内関係局等と密に連携を図りながら、適切な保安対策が図られるよう取組を推進してまいります。以上でございます。
◆野田雅之 国による水素保安戦略の中間取りまとめが公表され、実証事業においては、既存法令で対応するとのことでありました。また、その後の社会実装・商用段階では、技術実証により得られた安全確保を裏づける科学的データ等を踏まえ、新たな安全基準を設定するとのことでありました。
整備予定の液化水素基地においては、高圧ガス保安法等の関連法令に適合する施設の計画とのことでありますので、令和7年度からコンビナート地区の高圧ガス保安法の事務を所管することが予定されている本市の消防局における水素保安の取組について、消防局長に伺います。
◎消防局長(望月廣太郎) 水素保安の取組についての御質問でございますが、扇島地区に整備される液化水素基地に対し、消防局として適切な保安規制を行うため、水素社会の保安の在り方等について審議する国の水素保安小委員会や、大型貯蔵タンク等の技術基準について検討する高圧ガス保安協会に設置された水素等規格委員会及び同委員会の貯槽分科会に職員を参画させ、水素保安に関する最新の情報を把握するとともに、技術基準の検討段階において、消防機関としての意見が反映されるよう取り組んでいるところでございます。また、川崎臨海部における商用化実証の前段階として、液化水素の貯蔵等の技術実証が行われている神戸液化水素荷役実証ターミナルを本年11月に視察するなど、水素保安に関する知見を広げているところでございます。今後につきましては、国等が策定する新たな技術基準に基づき、高圧ガス保安法における許認可等の事務を適正に行うとともに、引き続き関係部局と連携し、液化水素サプライチェーンの保安の確保に取り組んでまいります。以上でございます。
◆野田雅之 今回、扇島地区に着々と進む世界最大級の施設の保安の考え方について伺いました。エネルギー資源の乏しい日本にとって、今後、経済や産業の発展において、安価で安定的に供給できるエネルギーの存在は欠かすことのできないものであり、国も含めて積極的な議論、取組が求められます。そこでは、地球温暖化の流れを一日も早く止めることが求められ、化石資源由来の燃料や原料をクリーンなものにしていく取組も重要であり、本市が進める川崎カーボンニュートラルコンビナートの形成、水素サプライチェーンの構築も大きく寄与するものであります。現在は、商用化に向けた実証実験の段階であり、物価高騰などの世界情勢などを踏まえると、まだまだ課題はありますが、しっかりとこの国の経済発展に貢献できる取組となるように期待するところであります。そこには、御当地である本市の安全は最優先事項であり、今後は、国等を含めた関係機関がしっかりと連携しながら適切な保安対策が講じられるよう、本市としてしっかりと関与し、関係事業者に対して指導助言を行い、何より安全で安心できる施設と保安体制の構築に取り組んでいただきたいと思います。
次に移ります。入札の制度について伺います。川崎市において、長年、工事や委託に関係するお仕事をされている専門工事事業者の方から、毎年、悲痛な叫びを受けております。その内容は、発注業務を専門で行う企業の受注ではなく、非専門工事の事業者が受注する案件が多く、その品質も含めて懸念を示す内容であります。今回業種は特に言いませんが、そういう要望を受けております。そこには現行の入札制度では、競争性の確保の度を超えたような応札者数になるケースや、明らかに専門工事事業者と違う企業の受注も見られます。当然このケースでは、主たる業務は下請、孫請などによる施工となることは目に見えております。市内に本社を置くなど、長年にわたり川崎市へ貢献してきた専門工事を行う事業者をしっかりと守り、育てていくことは、川崎市の未来に責任を持つこととなり、現在在籍する行政職員がしっかりと取り組んでいかなければなりません。そんな中、平成30年度には専門工事事業者育成型入札の試行をスタート、また、その後、自民党の代表質問や今年度に入り我が会派の浅野議員、また、公明党の春議員からも質問があったばかりです。それは、何人もの議員が現行の制度に疑問を持っていることにほかなりません。本日は、川崎市で登録できる業種、工事、委託、物品のうち、主に物品を除く入札制度を取り上げてまいります。
まず、この議論で頻繁に川崎市も使う競争性の確保とは何なのか、また、その確保には、どの程度の応札者数があれば確保されたと言えるのか伺います。また、現行の専門工事事業者育成型入札では、なぜ塗装、防水、内装の3業種に限定したのか伺います。また、この3業種で十分と言えるのか伺います。一定の資格を応札の条件にすることは極めて重要です。発注担当部局は積極的に応札の条件に専門的な条件を加えることがさらに望まれます。一方で、その条件が広く取得されているような場合には、より踏み込んだ制度の構築が望まれます。見解を伺います。
◎財政局長(斎藤禎尚) 入札契約制度についての御質問でございますが、競争入札におきましては、透明性や公正性の確保とともに、事業者の受注機会の確保に向け、多くの事業者に参加機会が開かれていることが望ましいものでございますが、応札者数については、具体的な指標はないものでございます。次に、専門工事事業者育成型入札につきましては、工事内容や発注状況を踏まえ、事業の活性化と事業者の育成等を図るため、業種を塗装、防水及び内装として、平成30年度から試行実施してきたところでございます。本制度につきましては、事業者の育成に資する一方、新規事業者の入札参加機会が制限されるなどの課題もございますので、その対象業種につきましては、慎重な検討が必要と考えております。また、入札参加資格の設定につきましては、品質確保に向け、業務内容に応じて同種業務の履行実績などの入札参加資格を設け、契約の適正な履行の確保に努めており、今後につきましても、事業者の御意見や他都市における取組も参考にしながら、必要な入札契約制度の改革に向けて取り組んでまいります。以上でございます。
◆野田雅之 答弁では、受注機会の確保に向け、多くの事業者に参加機会が開かれていることが望ましいとはいえ、具体的な指標はないとのことでありました。これだけ聞くと、多ければ多いほうがいいように聞こえてきますし、専門性を薄めたほうがいいようにも聞こえてきます。それは受注機会が大きく減少するとともに、品質の向上にもつながらないと考えております。また、専門工事事業者育成型入札については、工事内容や受注状況を踏まえたとのことですが、なぜ3業種になったのか全く見えてまいりません。このような話が出てくる以上は不十分と考えられ、その他の工種についても再度検討を求めておきます。
それでは、ここで他都市の取組を御紹介いたします。ディスプレーをお願いいたします。他都市においては、専門工事事業者にしっかりと受注してもらうような取組は既に行われております。政令指定都市に限定して調査をいたしました。岡山市は、工事と役務の区分において希望順位を申請できて、工事においては、原則1位の業種に登録がある者が参加できるということで回答いただいております。ちなみに、登録可能数は29業種に対して市内が3つしか登録できません。その他の地区は2つしか登録できないことになっております。北九州市におきましては、工事において申請可能で、1位の順位に限定された入札が実施されております。これはインターネットで公告を見ると、そういうものが見えてきました。ここも30業種に対して3つの登録しかできない状況であります。その中で希望順位をつけるということですね。横浜市においても、設計・測量等、あと物品・委託等が可能で、入札において採用することがあるということであります。また、一部の入札で採用している他都市で全ての区分が申請可能なのが、名古屋市、仙台市、相模原市、浜松市であります。一部の入札で採用で一部の区分で申請可能―これは堺市で建設工事、測量建設コンサルタントほかだったんですけれども、一部の入札で採用しているということであります。あと、業者選定や主に扱う業種の把握などに使用しているのが、一部の区分で申請可能としていると神戸市、千葉市、静岡市、熊本市から回答いただいております。専門工事を主たる業務とする事業者は、その専門の資機材や車両などを持ち、専門知識を有し、より良質な成果物を提供してくれるはずです。まさに、このような制度は育成も含めて極めて有効であります。ディスプレー、結構です。
それでは、藤倉副市長に伺います。災害協定を結ぶ団体や所属する企業は川崎市にしっかりと貢献してきたはずであります。その中には、専門工事に特化して事業を営む企業もあり、その方々はしっかりと業務を履行できる能力を有しております。その企業の受注機会を減らす制度は、専門性を有した企業の育成、品質確保の観点からも、しっかりと改善をしなければなりません。専門工事事業者の育成、品質確保や、さらなる品質の向上の観点などからも、専門的な技術を主たる業種として営む市内企業が受注することの必要性について見解を伺います。また、先ほど説明したような他都市でも実施されている希望順位の登録制度を設け、入札に活用する方法は極めて有効と考えますが、見解を伺います。
◎副市長(藤倉茂起) 市内専門工事事業者の受注機会の確保についての御質問でございますが、地域における専門工事事業者の受注機会の確保を図ることは、市民生活や地域経済を支えるとともに、地域のインフラ整備やまちづくりのための担い手を育成する観点から、重要であると認識しているところでございます。今後につきましても、他都市の入札契約制度を検証するとともに、事業者の御意見を十分に伺いながら、本市競争入札参加資格名簿への希望順位の登録制度など、さらなる制度改善に取り組んでまいります。以上でございます。
◆野田雅之 藤倉副市長からは、専門工事事業者の受注機会の確保は重要と認識している、また、事業者の意見も十分に伺う、希望順位の登録制度など、さらなる制度改善にも取り組むといただきました。川崎市でいうところの業種は、自治体ごとに区分も違いがあるのは理解をしております。令和7・8年度の入札参加資格申請は既に終了しておりますが、有効的なやり方の一つとして、ぜひ意見聴取や検証を早急に行い、さらなる効果的な制度の導入をお願いいたします。また、今回の調査では、各市の契約担当部署にメリットやデメリットもお聞きをしたので、一部お伝えをしておきます。ディスプレーをお願いします。一部なんですけれども、紹介させていただきますと、メリットとしては専門性の高い事業者との契約が可能とか、専門業者の参加で高品質な成果が期待できる、専門性を持つ業者を効率的に選定できる、意欲的な事業者の選定で入札不調の軽減が期待できる、過当競争の抑制効果が期待できる、主に扱っている業種の把握ができる。デメリットとしては、案件により応札者が限定される、なお、競争性が保たれない場合は案件ごとに入札参加資格の見直しを行う、応札者が少ない案件が発生する可能性があるとのことでありましたので御紹介させていただきます。また、別の制度となりますが、現在川崎市においては、登録可能な業種を6としておりますが、福岡市や北九州市は3つ、横浜市は4つとして、登録自体もより得意とする工種に限定されるよう制度化しております。また、岡山市では、工事において、市内を3、その他を2に絞っておりまして、浜松市では、建設工事において、市内本店業者は無制限として、それ以外は4つまでにするという制限を設けております。市内の事業者を差別化、守る取組を行っております。これらの自治体で3から4に絞り込むことができておりますので、川崎市においてもできないわけがありません。これらの登録業種数をより絞り込む取組も有効でありますので、検討を求めておきたいと思います。今年は市制100周年の年となりました。市内には、それ以前より業を営む企業も存在しております。その他の企業も含め、川崎市の成長に大きく貢献してきたはずです。今になって本当に残念と思わせるわけにはいきません。川崎市で仕事をしてきてよかったと思える制度の導入を求めておきます。市内企業の成長に向け、希望順位の登録制度や入札への導入、また登録可能な業種の数についても、今後継続して議論させていただくことを宣言して終わります。