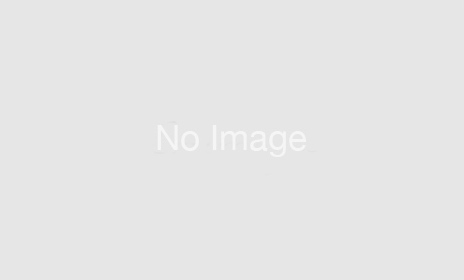◆野田雅之 おはようございます。通告のとおり一問一答で伺います。
保育事業について伺います。福祉施設の人材が不足し、保育所においても同様に保育士の確保が大きな課題となっています。本市の認可保育所における保育士の配置状況と、国基準に加えた川崎市独自の加配についての充足状況を伺います。また、本市の保育士等の配置状況は各区に配置されているほか、21の公立保育所がありますが、保育士の配置状況と充足状況を伺います。
◎こども未来局長(井上純) 保育士の配置状況等についての御質問でございますが、本市の認可保育所における市加配保育士の充足率につきましては、本年4月時点で休憩休息保育士が約92.7%、年休代替保育士が約78.8%でございまして、公立保育所については全ての園において市加配保育士を含め充足しております。以上でございます。
◆野田雅之 本市の区役所や公立保育所の保育士の配置及び充足状況が分かりました。ということは、民間は充足をしていないと言っております。それでは、なぜ民間の保育所の保育士は不足しているのか、本市と近隣他都市の補助制度や保育士確保施策の違いなどを含めて具体的な要因を伺います。
◎こども未来局長(井上純) 保育士の配置状況等についての御質問でございますが、認可保育所の市加配保育士が充足していない要因につきましては、昨今、保育人材の確保が困難な状況において、施設や法人ごとに職員の配置や処遇についての方針が異なるなど、様々な事由があるものと認識しておりますが、国の公定価格や地方自治体単独の上乗せ給付等について、地域により差があることも影響していると考えているところでございます。以上でございます。
◆野田雅之 答弁では、施設や法人ごとに職員の配置や処遇について方針が異なるなど、様々な事由があるとしておりますが、自治体単独の上乗せ給付等が地域によって差があることが影響しているとしております。後ほど改めて示しますが、川崎市がその差で影響を受けていることも要因の一つであります。施設側の立場に立って、しっかりと考えて対応することが求められます。それでは、本市でも保育士確保のために就職相談会を実施していますが、就職希望者がなかなか集まらないとお聞きをしますが、こども未来局長は就職相談会の視察をされたことがあるのか伺います。また、視察されていれば、いつどこに行ったのか、また、その相談会の概要、利用者人数やその際の様子、相談会の成果とその評価について具体的に伺います。また、人が集まらない状況をどのように捉えているのか、今後確保するためにどのようにしていくのか、取組項目を現状と目標の数値を示して具体的に伺います。
◎こども未来局長(井上純) 保育のお仕事就職相談会についての御質問でございますが、本相談会は、保育園で働くことに興味のある方と保育事業者とを対面でつなげるために開催しているものでございまして、私は、昨年8月に本庁舎2階ホールで開催した相談会を視察しました。その際の参加人数は13人でございましたが、参加者と事業者とで熱心に質問や相談が行われておりました。本市主催の相談会につきましては、昨年度7回開催し、参加者の総数は125人で、そのうち保育施設の見学につながったのは48人、内定者は18人でございました。本相談会のほか、人材確保に当たっては、保育士養成施設と連携した就職相談会及び見学会や、保育士試験対策講座などを実施しておりますが、より多くの参加者を確保するために効果的な取組が求められていると認識しております。相談会を含む保育所見学・体験型事業等への参加者数の計画上の目標値は3,100人としており、これまでこの目標値を達成しているところでございますが、今後につきましても、相談会の開始時期や開催時間を昨年度より早めるほか、各事業の広報内容の充実や広報先を拡大するなど、引き続き保育士確保に向けて取組を進めてまいります。以上でございます。
◆野田雅之 答弁では、局長は本庁舎で行われた相談会を視察されたとのことであります。しかしながら、その参加者は13人であります。事前のやり取りで、その際の参加法人数をお聞きしましたが、その数は15でありました。実に厳しい数字であります。1法人に対して1人以下の参加者数であります。保育士不足の重大さが現状の施策で対応できていない状況であります。また、7回の相談会の参加人数は125人で、平均約18名であります。他都市の事例や民間の事例を参考にするなど実施方法を検討する必要を感じております。また、それを考えると局長の視察された回はさらに少なく、相談会の手法や保育士不足の解消を大きな課題と捉えるべきであります。それでは、本市の認可保育所の施設数、認可保育所に所在する障害児の人数と施設数、平均障害児在園数について伺います。
◎こども未来局長(井上純) 保育所における障害児等の受入れについての御質問でございますが、令和6年度に障害児保育費認定を行った児童は531人となっておりまして、認可保育所435施設のうち受入れを行っている施設が240施設、行っていない施設が195施設、受入れを行っていない施設を含めた1施設当たりの平均受入れ人数は約1.2人となっております。以上でございます。
◆野田雅之 ただいまの答弁では、435の施設に対して受入れ施設が240とあり、率にして約55%です。残りの約45%は受入れをしていないということになります。また、平均の受入れ人数は約1.2人ということです。それでは、民間の認可保育所で障害児が一番多く在籍する園では何名の障害児が在籍しているのか伺います。また、障害児が多く在籍する園について、その理由と背景を伺います。
◎こども未来局長(井上純) 保育所における障害児等の受入れについての御質問でございますが、令和6年度に障害児保育士認定を行った児童が最も多い認可保育所の受入れ人数は8人であり、個別の状況について、その要因を明確にすることは難しいものと認識しておりますが、市全体の背景としては、社会状況の変化や保育ニーズの多様化に伴い、障害児を含む特別な支援を必要とする児童等の入所希望が増加していることなどがあると考えております。以上でございます。
◆野田雅之 答弁では、障害児を含む特別な支援を必要とする児童等の入所希望が増加しているとのことでありました。しかしながら、先ほどの答弁からは約45%の施設が受入れをしておりません。また、平均は1.2人にもかかわらず、極端に多い8人を受け入れている園もあり、あまりにも偏った入所決定をしていると言わざるを得ない状況であります。事前の調査では、受入れ人数が8人が1施設、6人が2施設、5人が7施設、4人が18施設となっておりました。受入れゼロが195施設であり、受入れ施設の240のうち僅か28施設で、531人のうち約4分の1の127人を受け入れております。園によっては対応を苦慮しているとお聞きしております。本当に施設側が納得して受け入れているのか、見解を伺います。また、障害児受入れは園の義務とのことですが、利用者の希望があった場合、人材体制が整っていなくても無制限に受け入れなくてはならないということになるのか伺います。
◎こども未来局長(井上純) 保育所における障害児等の受入れについての御質問でございますが、本市といたしましては、保育所等の入所に当たり、保護者には施設を見学した上で申込みを行うよう案内しており、入所決定においては児童の障害特性や、その他個別の御事情等、区役所で把握している情報をできる限り速やかに施設に提供し、御理解いただくよう努めております。また、認可保育所につきましては、子ども・子育て支援法第33条第1項において、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならないと規定されており、本市の川崎市民間保育所の認可・運営基準に関する取扱要綱第6条第1項において、障害児の受入れは全施設で実施するものとするとし、第3項で、障害児の受入れに当たり、通常の職員体制では、受入れが困難な場合には、職員の加配を行うものとすると規定しているところでございます。以上でございます。
◆野田雅之 答弁では、入所決定では諸事情などを施設に提供、御理解いただくように努めているとのことです。とはいえ大きな偏りを感じております。今後も調査をしたいと思っております。また、受け入れるのが園の義務とのことですが、入園して初めてその児童の状況が分かり、対応に苦慮する状況は、子ども、保護者、事業者にとって適切な環境なのかが疑問であります。障害を持つお子様が適切な保育を受けられるよう支援する義務が行政にはあるはずですが、見解を伺います。
◎こども未来局長(井上純) 保育所における障害児等の受入れについての御質問でございますが、乳幼児期の児童の発達は心身ともに個人差が大きく、一人一人の発達過程を踏まえた保育を展開する必要があり、障害児等につきましても個人差に配慮した保育を行うことが児童の健全な発達などにおいては重要であるため、本市といたしましては、障害児等への対応を含め、適切な保育の提供について施設を支援することとしており、また、指導を行う責任があるものと認識しております。以上でございます。
◆野田雅之 ただいまの答弁では、本市として障害児等への対応を含め、適切な保育の提供について施設を支援すると明言をされました。では、保育所では障害児は受け入れることとなっておりますが、保育士不足の昨今、入所内定者が決まる12月、1月頃から園側が職員を急遽配置することは非常に困難なはずであります。加配できなかった場合、当該児童の処遇はどうなるのか伺います。また、個別な対応がなされず、健全な成長、発達を阻害することにならないのか伺います。1人の保育士が障害児に個別で対応している間、他の児童に目が届かず事故が起こることも想定されます。一旦入所してしまえば、あとは園任せということなのでしょうか、見解を伺います。また、事業者の努力で職員を多く配置しても十分な財政支援がなければ赤字となるのが実情であり、子どものことを思い、看護師や保育士の加配を頑張って実施している施設の苦労が報われていないこのような状況を市としてどのように捉えているのか伺います。
◎こども未来局長(井上純) 保育所における障害児等の受入れについての御質問でございますが、新年度の入所につきましては、11月上旬までに利用希望者からの申込みを受け、各区の児童家庭課が内容確認等を行った後、12月中旬から1月上旬にかけて利用調整会議を実施し、各施設に対して入所予定者をお知らせしております。施設においては会議結果や入園前健康診断及び面談内容を踏まえて、新年度に向けた保育士の配置等の準備を進めておりますが、期間が十分に取れないため必要な職員の配置が難しいといった声も伺っているところでございます。本市といたしましても、保育所の入所決定においては児童に関する情報を速やかに提供するよう努めており、適切な保育の実施に向けた支援、指導として、実際の保育現場において各区の保育・子育て総合支援センターや保育総合支援担当が障害児等の受入れを行う施設に対して、児童の発達や具体的な関わり方の理解及び保護者への支援の学びを深めることを目的として、発達支援研修等を各区で年2から4回実施していることに加え、施設から相談があった場合には訪問し、実際に保育の様子を見た上で助言を行うとともに、保育の参考として公立保育所の対応事例を伝える等、施設の状況に応じた支援を行っております。また、昨今の保育士不足等の影響もあり、保育士の確保が厳しい状況等もございますので、財政的支援として、国の公定価格に上乗せして本市独自で障害児保育費のほか、休憩休息保育士、年休代替保育士の雇用費や、看護師等職員の雇用に係る各種加算による給付を行っているところでございます。以上でございます。
◆野田雅之 それでは、近隣の横浜市の障害児保育費の額について状況を伺います。また、障害児の入所については職員の加配がしやすくなるよう、障害児の認定時期を早めるなどの対応は考えられないのか伺います。
◎こども未来局長(井上純) 保育所における障害児等の受入れについての御質問でございますが、他都市の状況につきましては、対象となる児童の範囲や認定基準等、制度の仕組みが自治体によって異なるため、一概に比較することは難しいところでございますが、横浜市では令和6年度の取扱要綱によりますと、対象となる児童1人当たり、認定区分等に応じて最大37万200円の加算を行うこととされております。障害児保育費の認定につきましては、これまでも段階的にスケジュールの前倒しを図ってきたところでございますが、今年度からは事務処理センターによる1次審査のほか、施設の意向に応じてオンラインによるヒアリングを新たに導入する等、認定の迅速化に向けて取り組んでおり、今後につきましても速やかな支給につながる手法について検討してまいります。以上でございます。
◆野田雅之令和6年12月の答弁では、民間保育所における障害児保育費の認定の時期については、障害者手帳等の交付を受けている子どもや前年度に認定された子どもについては6月下旬、また、障害者手帳等の交付のない子どもについては8月下旬にそれぞれ認定を行っているとのことでした。しかしながら、新年度の4月から職員を配置してから認定されるまでの間、人件費は事業者が負担しているとのことです。障害児が何人も在園する園では数百万円単位で立て替えているとのことであります。前年に認定されている場合はもちろん、初めて認定申請する児童についても概算払いで支給するなどの措置ができないのか、見解を伺います。障害児認定に申請しても、必ず認定されるかは分からない状況であっても、個別の支援が必要であれば職員を配置するよう努力をしている園もあります。加配できていない場合、職員全体が疲弊、離職につながることも容易に想像ができます。そこで、障害児の認定の基準には軽度、中度、重度の基準がありますが、正式にはどこに定められているのか、また、誰が判断するのか伺います。また、入所時には分からず、保育所での生活において気になることが見つかり、年度の途中で加配職員を置くこともあるとのことです。その場合、再度の障害児認定の手続について伺います。加えて費用の支給時期がいつになるのか伺います。
◎こども未来局長(井上純) 保育所における障害児等の受入れについての御質問でございますが、乳幼児期の児童につきましては、特に年齢による発達状況や特性の変化が大きく、障害児保育費の適正な給付に当たっては、対象となる児童のその時点の状況を十分把握し、要件を満たしているかどうかを適切に判断した上で支払いを行う必要があると考えております。障害児保育費認定の基準につきましては、川崎市保育所子どものための教育・保育給付費等支給要綱において定めており、対象となる児童が身体障害者手帳等の交付を受けている場合は、その等級に応じて認定するほか、必要に応じ保育士資格を有する職員と担当職員による施設への訪問等により、保育状況などを確認した上で認定を行っているところでございます。また、年度途中での認定につきましても随時申請を受け付けており、申請に合わせて速やかな審査と給付に向けて適時適切に対応しております。以上でございます。
◆野田雅之 保育士不足の中、各保育所では定員割れを起こし、委託料が減り、経営の悪化が進み、それでも何とか工夫をして配慮しながら運営している状況が見えてきております。障害児加算については障害児の程度に合わせた費用が支給されていますが、そもそも障害児の程度に合わせた額と、保育時間を勘案した費用を支給するべきではないでしょうか。川崎市の障害児保育料は最大28万5,400円です。制度の違いがあるとはいえ、先ほどの答弁における横浜市の令和6年度の最大加算額は37万200円であり、今年度はさらに加算され41万4,600円となり、本市よりはるかに高い状況であります。また、世田谷区では障害児等保育加算としては12万9,420円ですが、様々な制度の加算を加えると川崎市を超える額となるとのことであります。保育士本人の給与にも直結する加算であり、改善の必要性を感じます。常に他都市の事例などを気にかけ、本市の制度の弱さを補うことが求められます。また、認定時期のずれによる施設側の持ち出しは大きな問題です。8名も抱える園ではそれだけで数百万円、幾つかの園を運営する法人では全体で相当な額に上ることも想定できます。既に入園している園児の対応も含めて早急な検討をお願いいたします。保育所では人材不足、人材育成、障害児への適切な対応、また、昨今では外国人が1園に何十人も入園している状況もあるとのことです。日本語の話せない親子への対応に苦慮して職員が疲弊、離職が問題になっている園もあるとお聞きをしております。少子高齢化が進む中、福祉施設の人材確保や育成等、問題も多くあります。東京、横浜に囲まれ不利な条件もありますが、川崎市の早急な対応が求められます。先ほども述べましたが、本市として障害児等への対応を含め、適切な保育の提供について施設を支援すると明言されました。市職員が現場を直視し、何より園側の立場に立ち、園児にとって最良の保育運営ができるよう、早急によりよい制度を構築するよう強く求めます。これからも、これらの問題をまた引き続き取り上げてまいります。
続きまして、以前から取り組んでおります、国も健康格差の縮小や生涯を通じた齲蝕予防に必要と認めるフッ化物洗口を小中学校に導入することについて伺います。新年度になり予算も増額され、現在、今年度の取組の進め方を歯科医師会と相談しているとのことであります。こんな中、今回、以前より要求してきました児童の虫歯の本数についての分かりやすい新たなデータが示されました。ディスプレーをお願いいたします。これは、とある区の令和5年の未処置の歯が少なかった学校、A校における令和6年の未処置の歯、並びに虫歯になる前の歯――COはまだ示しておりませんが――の本数ごとの人数。A校は758名の学校で、1本持っている1年生が3人、2年生が1人、5年生だと2本持っている子が1名という見方になります。小学校1年生から6年生の歯の本数の目安は、乳歯が20本、親知らずを除いて永久歯が28本ぐらいに小学生のうちに生え変わってまいります。次にB校です。同じ区のあまり芳しくない学校であります。この学校は12本持っている生徒とか、11本持っている生徒とか、9本とか5本とか8本とかですね。しかも生徒数は先ほどの学校の3分の2であります。このような状況で、偏りが非常にあるということが見られます。これが、27人と75人というのは、さっきの人数を足した数字ですね。見やすくしましたけれども、生徒が多いほうが未処置数が少ないと。B校のほうが生徒数は少ないけれども未処置の数は多いということとなっております。
この状況を見て、歯科医師の先生から見解を伺っております。今回のパワーポイントの資料では、重症化している生徒が放置されている状況が分かります。このケースの場合、本来早い時期の受診勧告を促す結果となります。今回のデータで未処置の歯の多い生徒は一本も治療していないと想定できます。そういう子どもの中には、貧困によって歯ブラシやフッ化物入り歯磨き剤を買えない子どももいる可能性もあり、そもそも歯磨きの習慣が確立されていないかもしれません。だからこそフッ化物洗口をすることは大変有意義だと言えますということでありました。加えて、日本歯科医師会、ここに出ておりませんが、日本学校歯科医会による健やかな子育て支援のチェックリスト(学校健診)の解説によりますと、未処置の齲蝕が多いことはネグレクト等への気づきにつながります。ネグレクト等と貧困は密接な関係があります。自分用の歯ブラシがないため口腔内が不潔で、重症な歯肉炎が見られることもある。歯科健診後のお知らせや治療の勧告等への対応を行わない養育者は子どもへの関心が薄い傾向があります。必要な医療を受けていないのはネグレクトですとのことでありました。それでは、今後もデータの提供を求めてデータの分析を行っていきますが、これらの教育委員会が持つ貴重なデータを分析して今後の施策に役立てるべきですが、見解を伺います。
◎教育次長(田中一平) 歯科健診のデータ等についての御質問でございますが、児童生徒の歯科健康指導の取組を進める上で、健診データを整理、分析することは有効であると認識しておりますので、今後も学齢期別の状況把握など詳細に分析した結果を課題解決に効果的に活用しながら、健康管理の充実に努めてまいります。以上でございます。
◆野田雅之 答弁では、歯科健康指導の取組を進める上で健診データを整理、分析することは有効と認識、学齢期別の状況の把握など詳細に分析した結果を課題解決に効果的に活用しながら健康管理の充実に努めるとのことですが、しっかりとお願いをいたします。
ディスプレーをお願いします。今回、その2校の未処置の歯のデータ以外に、虫歯になる前の歯、いわゆる要観察歯――COという虫歯になる前のデータも出てきておりました。先ほどの非常に状況の悪い学校は、やはり虫歯になる前のデータも非常によくないという結果であります。5本とか7本とか、そういう所見が見られるところであります。このデータについても歯科医師の先生に確認をしておりますが、このCOについては、まさにフッ化物が歯の再石灰化を促し、修復を図ることができることが認められており、小学校等でのフッ化物洗口は大変有意義な取組となりますとのことでありました。今回新たなデータを示すことができました。これは以前より歯科医師の先生が指摘をしてきました、現在虫歯が少なくなってきている傾向だが、本当に地域とかによっては、すごく多く本数を持っている、どかんと多く持っている子がいるということが初めて実証されました。今後はさらに、ちょっと厳しい学校があるのは分かっておりますので、データの開示を求めていきたいと思っております。そして、まさにこれが健康格差であります。だからこそ近年国も必要と認めておりますし、マニュアルも改定を進めていたりするところであります。だからこそ、本市においても学校での実施が望ましいということとなります。このような子どもたちが自宅でやることは極めて困難で、学校での洗口が大変有効なことは十分に分かっていただけると思います。ぜひ来年度は、できれば全校実施に向けた準備を、また、そうでなければ、まずはモデル校での通年実施を目指していただくよう強く要望いたしまして質問を終わります。